吉備真備(きびのまきび)【695年~775年 享年80歳】

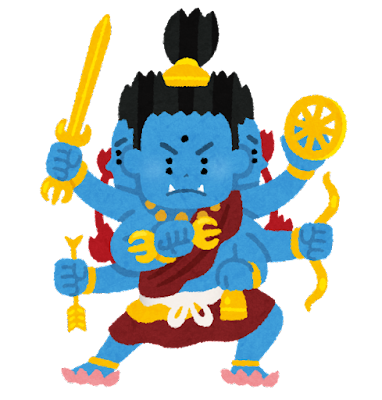
こんにちは、reopaです。case33は「吉備真備」さんです。
学者であり政治家でもあり、唐に留学し儒学・天文・兵学などに
通じた吉備真備さんは、どんな人物だったのでしょうか。
【銅像所在地】
【銅像所在地:岡山県 小田郡 矢掛町 東三成 吉備真備公園】
吉備真備公園は、岡山県出身の古代史の英傑、吉備真備公の遺徳を偲んで設けられた
公園で、平成19 年に「日本の歴史公園100 選」(日本公園緑地協会)に選定されました。
真備は、日本へ最初に囲碁を伝えたと言われており、日本における囲碁の開祖として、
公園内にある居館跡には「囲碁発祥の地」記念碑が建立されています。
公園内には、真備在唐中の印象を偲んで建てられた、中国屋敷を再現した「館址亭」があり、
その他にも「絵巻石屏風・大碁盤・日時計・産湯の井戸」などが、整備されています。
この公園内には、吉備真備一族の菩提寺といわれている「吉備寺や墳墓」もあります。
【家族構成】
父:下道圀勝(しもつみちのくにかつ) 母:楊貴氏(やぎし)
兄:下道乙吉備・下道直事・下道廣
妻:不明(ふめい)
息子:長男 吉備泉(きびのいずみ) 長女 吉備由利(きびのゆり)
【人物像】
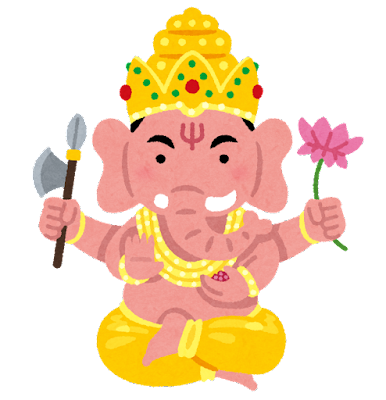
真備さんは、才能豊かで多方面にその才能を生かした天才と言われる人物。
性格は温厚・誠実・潔白・忍耐強く人からの信頼も厚く人徳を兼ねそろえた
人物と言われているね。
【時代背景】
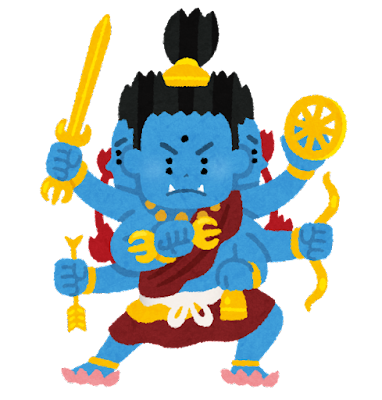
阿倍仲麻呂さんも、玄宗皇帝に認められて唐で出世し、日本に帰る
ことは無く生涯を中国で過ごしたんだ。帰国しようとした船が難破して
帰ることが出来なかったと言う、話もあるんだ。
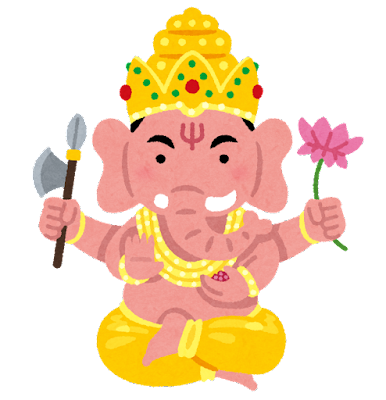
真備さんの活躍を面白く思っていなかった人がいて、政治の中枢から
排除しようとしていたんだね。
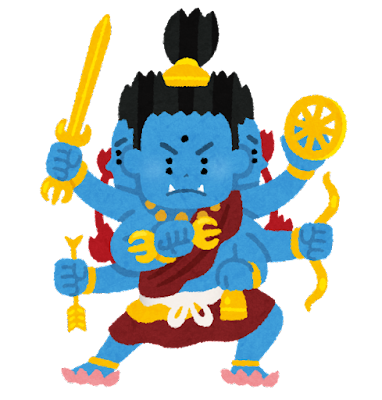
真備さんが、身分の低い家柄出身だったからだけではなく、真備さんの
才能豊かな面に嫉妬していたとも言われているんだよ。
752年(天平勝宝4年)真備は、唐で高名な僧侶である鑑真(がんじん)を
日本に連れてくる事を主目的に、遣唐副使となり再び唐に向かいます。
真備らにより任務は果たされ、鑑真の来日は日本に大きな影響を与えることになります。
その後の764年(天平宝字8年)孝謙天皇と道鏡(どうきょう)に抑圧された、
藤原仲麻呂が政権を奪うために反乱を起こします。この乱は「藤原仲麻呂の乱」と呼ばれ、
真備は中衛大将として追討軍を指揮し、唐で学んだ兵法を生かし優れた軍略で、反乱の
鎮圧に功績を挙げました。
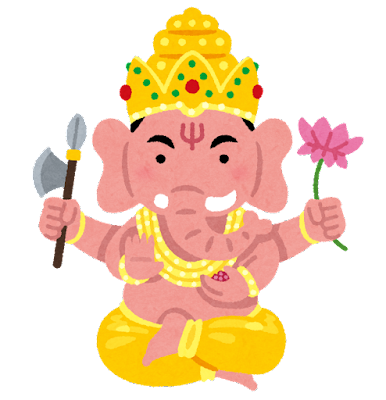
真備さんが2度目に唐に向かった時は、唐に滞在し官職に就いていた
阿倍仲麻呂さんが、案内役として吉備真備をサポートしたんだよね。
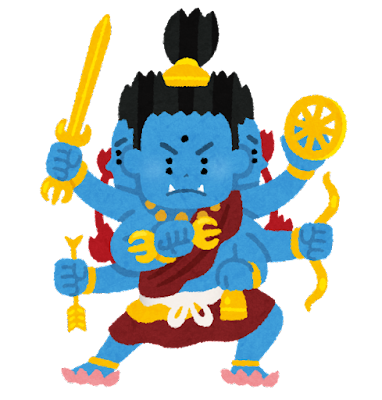
鑑真さんの来日に際しても、阿倍仲麻呂さんは力を貸してくれたんだよ。
その後、孝謙天皇が再即位して称徳天皇(しょうとくてんのう)となり、その下で
右大臣に任命されました。学者という身分でありながら右大臣にまで昇進した人物は、
学問の神様で有名な菅原道真と吉備真備の二人しか日本にはいません。
称徳天皇の死後、770年(宝亀元年)光仁天皇が即位し、真備は高齢を理由に退職を願い
出ましたが認められず、翌771年に再び退職を願い出て許可が下りました。
真備はその4年後に亡くなったと伝えられています。
【名言】
「長生の弊、却りて此の恥に合ふ」
(長生きした為に、とんだ恥をかいてしまったことよ)
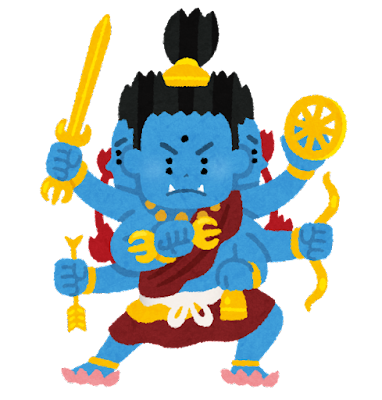
真備さんが、子孫に向けた訓戒のために薯したといわれる「私教類聚」
(しきょうるいじゅう)は、現代にも通じる内容だと思うから二つほど
紹介しておくよ。「言葉を選ぶこと」「まず考えてから行動すべし」
【エピソード】
陰陽道の祖は真備だと伝えられています。日本の陰陽師で最も有名な人物は
安倍晴明(あべのせいめい)ですが、晴明の系譜をたどると真備に行き当たる様です。
真備は唐から、陰陽道の聖典「金烏玉兎集」を持ち帰ったと言われ、晴明は幼い頃に
「真備の書物」で陰陽道を学び、奥義のすべてを受け継いだとされています。
さらに「今昔物語集」の中では、玄昉を殺した藤原広嗣(ふじわらのひろつぐ)の霊を
陰陽道の奥義によって鎮めたと伝えられています。
片仮名(カタカナ)をつくった人物は真備という説があり、その根拠は
南北朝時代の書物である「倭片仮字反切義解」の中に、真備が片仮名を草案したと
いう記述があるため、片仮名を作ったのが真備であると言われています。


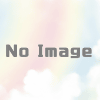










ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません